情報セキュリティ研修のヒント
研修範囲が広い情報セキュリティ分野
情報セキュリティ研修とひと口に言っても、その範囲はどこまでも広がってしまいます。あなたの会社や部門で実施する際には、焦点を絞った方がいいでしょう。特にリスクが大きく、発生する可能性が高いもを優先しましょう。
情報セキュリティについて関心を持っている人はあまりいません。何をしなければいけないのか理解できていないことを前提に研修は企画すべきです。
いきなり高度な内容のことを教育しても、かんたんに身につくものではありません。最低限やるべきことを決めて、シンプルに始めることをおすすめします。
研修の前にルールを決めておく
社内にある貴重な情報を適切に管理するには、遵守すべきことと禁止事項を明確にする必要があります。特に禁止事項については就業規則に懲罰を明記し、社員全員に対し十分理解させなければなりません。
”何がいけないのか”をわかりやすく研修会で伝えて、ルールを守れるように導くことが大事です。
守るべきもの 個人情報
個人情報はどの部門にも存在します。お客さまだけでなく、社員のも個人情報として適切に扱わなければなりません。
お客さまの個人情報を取り扱うことの多い、営業やサービス、情報システム部門などでは研修に時間を割いた方がいいかもしれません。
こちらも参考にしてください >> 個人情報保護研修のヒント
守るべきもの 営業秘密
「営業秘密」というのは、不正競争防止法の中で定義されていることばで、一般的には「企業秘密」や「トレードシークレット」などと呼ばれています。
原料や製品などの製造プロセス、独自に構築してきた販売マニュアル、重要な販売先リスト等々、万一情報が漏れてしまうと大きな損害を被るような情報をさします。
不正競争防止法により権利侵害の場合には、差し止めや損害賠償等の請求ができます。また侵害者には罰則が科せられることもあり、情報漏えいの抑止力として有効です。
不正競争防止法第2条15の2に次の記載があります。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
上記3つの要件を満たしていないと「営業秘密」には該当しません。社内的には”秘密として管理する”ことがまず重要です。
そして、そのことを研修などで周知徹底しなければなりません。「営業秘密は何があっても漏えいさせてはならない」という意識を全社員に持たせましょう。
経済産業省のホームページに有益な情報が掲載されていますので活用しましょう >> METI営業秘密のページ
守るべきもの その他
企業や組織によって情報セキュリティの対象になるものはさまざまです。同じ社内でも部門が違えば対象も異なります。
自社、自部門にとって管理し、守るべき情報資産は何なのかを明確にして研修に取り入れてください。
情報漏えいリスク低減のために
情報セキュリティのためのルールを就業規則にも反映することはすでに説明しました。さらに細かな内容は「情報セキュリティ管理規程」などを作成し、掲載
するのも方法です。
ITリテラシーがあまり高くない社員もいることを前提に、できるだけわかりやすい内容で掲載しましょう。
文書だけでわかりにくい場合は、画像やイラストなどを活用して表現します。
下記の画像はID、パスワード管理の重要性を啓蒙するために研修で使用したものです。
ID、パスワードを忘れてしまうために、パソコン本体に付箋で貼り付けていた人がいたので、それがどういう行為かを理解してもらいました。

次のイラストはパスワードの長さや組み合わせがどれだけ大事かを理解してもらうために作りました。
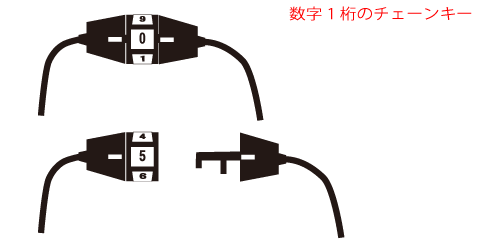
意識持続するためのメール研修活用
情報セキュリティ研修が終わると、まもなく意識が低下し始めます。どうしても「自分とは関係ない」という気持ちがはたらいてしまうのです。
どんな研修や勉強会も同じですが、繰り返し刷り込みするしか定着させる方法はありません。そこでおすすめしたのが、メールによる研修です。
研修といっても月に1〜2回、情報セキュリティに関する事例を紹介するのです。残念ながら漏えい事故は頻繁に発生しています。ネットで検索すれば、ヒットします。
その中から自社の環境に近いものを選び、事故抑止に活用するのです。実際の事例だとリアル感があり、関心をもってもらいやすいです。
これを繰り返すことで、意識は高まっていきます。
未然に事故を予防する”相互関心”
情報セキュリティ研修や学習をいくらやっても、漏えいリスクが0になることはありません。特に故意による漏えいだと防ぐ手段が限られてきます。
そのような故意による漏えいリスクを抑えるには、社員同士が互いに関心をもつことが大事です。
近くの同僚や上司部下に関心をもっていれば、態度の変化に気づくはずです。また、そのような状況に陥る前に誰かがフォローしたり、相談を受ける可能性が高くなります。
ぜひ、職場の仲間とは”相互関心”の気持ちをもって接してください。
